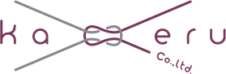スモールビジネスを行うには法務の知識が必要だと言われているけれど、具体的にどのようなことを学べばよいのかよくわからず困っている人はいませんか?
この記事では、法務とは何かからスモールビジネスにおける企業法務の相談先まで詳しく解説します。
法務とは?
法務とは法律に携わる事務、職務、業務のことです。
企業において行われる法務は「企業法務」と呼ばれ法務部がその業務を担当します。
企業法務において法務部が果たす役割は次の2つです。
| 項目 | 概要 |
| 攻めの法務(企業活動のアクセル) | ・法律を武器として有利な企業活動を後押しする |
| 守りの法務(企業活動のブレーキ) | ・社内や社外のトラブルを未然に防ぎ企業活動のリスクヘッジ(リスクをあらかじめ予測しそれに対応できる体制を整える)をする |
顧問弁護士は違法か適法かの判断をするのが主な仕事となりますが、法務部は企業活動において法律を基に企業の成長を助ける役割を果たしていると言えるでしょう。
スモールビジネスの企業法務で使われる主な法律
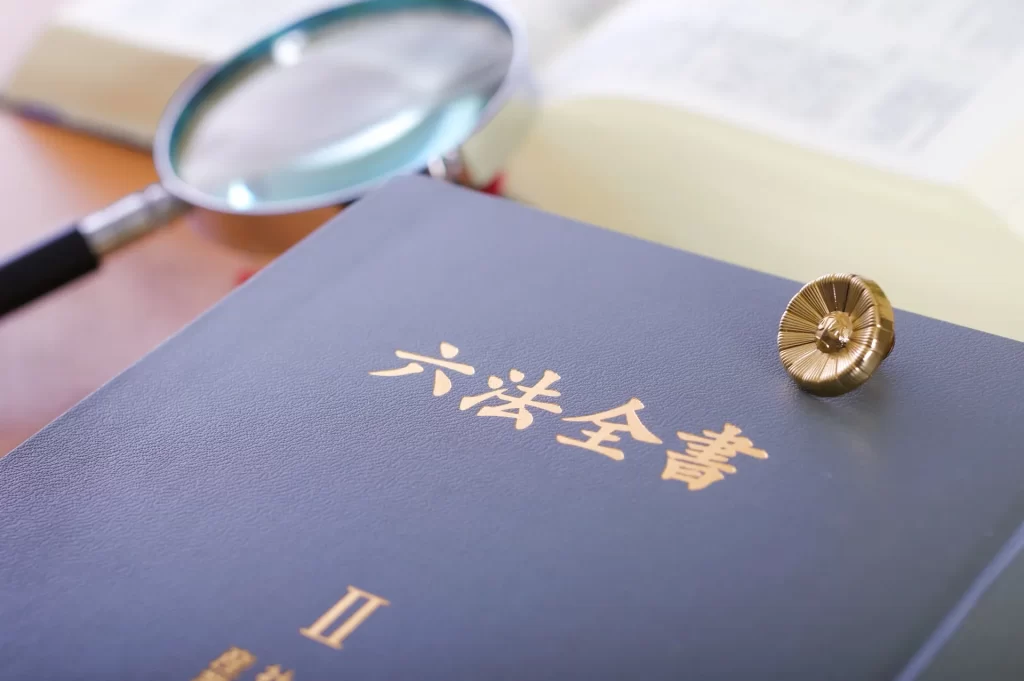
スモールビジネスの企業法務ではどのような法律が主に使われるのでしょうか。
「ヒト」「カネ」「モノ」の3つに関わる法律をそれぞれご紹介します。
ヒトに関する法律
ヒトに関する法律の中では、主に次の法律が使われます。
| 法律の分類 | 法律名 | 概要 |
| 労働法 | 労働基準法 | ・労働条件の基準を定めた法律 |
| 男女雇用機会均等法 | ・企業の雇用における男女の機会均等・待遇の確保を目的とした法律 | |
| 育児・介護休業法 | ・育児や介護と仕事の円滑な両立を支援する法律 | |
| 労働者派遣法 | ・派遣労働者を守るための法律 | |
| 商法 | 会社法 | ・会社の設立、組織、運営、管理について定めた法律 |
| 民法 | 民法 | ・個人間の取引、権利、義務、身分に関する規定を定めた法律 |
個人にについての規定を定めた民法が、なぜスモールビジネスの企業法務に置いて重要なのか一見わかりにくいのですが、スモールビジネスの経営者はそのほとんどがオーナーでもあるため、会社法で定められた「所有と経営の分離」が徹底されていないのが現状です。
そのため民法における家族法(第4編の「親族」と第5編の「相続」を合わせた部分)の部分を理解しておかないと、オーナーの相続問題が会社の経営に影響を及ぼす可能性が出てきます。
モノに関する法律
モノに関する法律の中では、主に次の法律が使われます。
| 法律の分類 | 法律名 | 概要 |
| 民法 | 製造物責任法(PL法) | ・製造物の欠陥で個人の生命、身体、財産に損害が生じた場合損害賠償を求めるための法律 |
| 医事法 | 薬事法 | ・医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品に関する運用を定めた法律 |
| 行政手続法 | 食品衛生法 | ・飲食による衛生上の危害を防止し食品の安全性を確保するための法律 |
| 環境法 | 廃棄物処理法 | ・廃棄物の排出抑制、適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分などの処理で生活環境を守るための法律 |
| 地球温暖化対策法 | ・国内において地球温暖化対策を推進するための法律 | |
| 経済法 | 独占禁止法 | ・資本主義の市場経済で健全で公正な競争状態を維持するための法律 |
| 下請法 | ・下請け業者の保護を目的とする法律 | |
| 知的財産法 | 知的財産基本法 | ・知的財産の創造、保護、活用に関する国の基本的な方針を定めた法律 |
| 特許法 | ・発明の保護と利用を図ることで発明を促し産業の発展に貢献するのを目的とする法律 | |
| 実用新案法 | ・物品の形状や構造、または組み合わせについての考案の保護と利用を図ることで産業の発展に貢献するのを目的とする法律 | |
| 意匠法 | ・意匠(デザイン)を公開する代わりにその使用や譲渡を独占できる制度を定めた法律 | |
| 商標法 | ・商標(自社の取り扱う商品やサービスを他者と区別するために使用するマーク)を使用する者に独占的な使用権を与えるための法律 | |
| 著作権法 | ・著作者の権利を保護することを目的とした法律 |
自社のビジネスを進める上で他社の権利を侵害しないようにするためにも、モノに関する法律を知っておくのは大切なことです。
カネに関する法律
カネに関する法律の中では、主に次の法律が使われます。
| 法律の分類 | 法律名 | 概要 |
| 民法 | 民法 | ・個人間の取引、権利、義務、身分に関する規定を定めた法律 |
| 民事再生法 | ・債務返済ができず経営が行き詰まった会社、個人事業主、借金返済が難しくなった個人が債権者の同意の上で事業再建をするための法律 | |
| 商法 | 商法 | ・営利目的の企業や個人の活動や手続きに関するルールを定めた法律 |
| 保険業法 | ・生命保険会社と損害保険会社の業務範囲などを定める法律 | |
| 会社更生法 | ・経営困難な会社が営業を続けながら更生手続を進めるための法律 | |
| 金融法 | 金融商品取引法 | ・金融商品の販売や勧誘について定め取引の公正と投資家の保護を目的とした法律 |
| 貸金業法 | ・クレジットカード会社や消費者金融などの貸金業者が業務を適正に行うための法律 | |
| 倒産法 | 破産法 | ・破産手続に関する法律 |
民法における契約法(第3編第2章)が日本における契約についての法律の中核となっています。
しかし民法は個人間の取引について定めた法律のため、企業で行われる取引において商法で定められている項目については、そちらが優先されるのです。
また民法では第709条において一般不法行為、第714条以下において特殊不法行為について定めており、他人の権利や利益を侵害した場合損害賠償ができるよう定められています。
参考:e-GOV法令検索
スモールビジネスにおける企業法務の内容

スモールビジネスにおける具体的な企業法務の内容は次の通りです。
| 項目 | 概要 | 具体例 |
| 契約・取引法務 | ・契約書を作成し法的に問題がないかチェックする(リーガルチェック) | ・契約書審査(契約書レビュー)・契約書作成(契約書ドラフト) |
| 機関・組織法務(ガバナンス) | ・会社の内部機関の活動が法的に問題がない内容で行われるようサポートする | ・株式の発行・組織再編・株主総会の対応・取締役会の運営 |
| コンプライアンス・社内規定 | ・法令や規定を順守するよう社内に働きかける | ・社内規程を定める・相談窓口の設置・マニュアル作成・コンプライアンス研修の実施 |
| 紛争・訴訟対応 | ・顧客からのクレームを受けた場合や、取引先や行政機関との間で紛争が起こった際の対応を行う | ・訴訟の準備・代理人弁護士の選任・外部弁護士との協議や相談・紛争解決に向けた社内での情報収集 |
| 法律相談 | ・他部署からの法律相談の対応 | ・企業活動に生じる法的なリスクを調査・周知 |
| 債権回収・債権管理 | ・売掛金、売買代金、請負代金などの債権を回収する・予防的な債権の保全や債権管理をする | ・直接的な債権回収(催告、民事保全手続、支払督促、訴訟など)・取引先の信用調査・証拠書類の確保・債権保全のために有効な契約条項を設けた契約書の作成・時効の管理 |
| 労務・労働問題への対応 | ・労務管理や労働問題への対応をする | ・セクハラ、パワハラなどのハラスメント対応・就業規則や雇用契約書の作成・労働環境が労働基準法に準拠しているかどうかのチェック・訴訟・労働審判対応・問題社員対応・人事異動、昇格、解雇などに関する紛争対応・労働組合からの団体交渉の対応 |
| 法令調査 | ・法制度の変化を調査し社内に周知する | ・国内の法令調査・海外展開をしている会社の場合海外の法令調査 |
スモールビジネスのうちから法令順守意識を高めておくことで、会社が少しずつ大きくなっても企業法務が滞りなく行われる土台を築くことができるでしょう。
スモールビジネスにおける法務対応の現状

スモールビジネスにおける法務対応は、現状どのような形で行われているのでしょうか。
2019年に東京商工会議所が921件の中小企業を対象に行った「中小企業の法務対応に関する調査」の結果から3つご紹介します。
スモールビジネスが法務に関して抱える課題
「中小企業の法務対応に関する調査」で会社が法務に関して抱える課題についてたずねた所、次のような結果が出ました。
| 課題 | 割合 |
| 人材不足 | 47.6% |
| ノウハウの不足 | 45.7% |
| 全社的な法務意識の醸成 | 32.1% |
| 法務人材の育成の困難さ | 26.8% |
| 組織内の体制構築 | 24.2% |
スモールビジネスが法務に関して抱えやすい課題は人材やノウハウの不足、また会社全体における法務意識の醸成であることがわかります。
法務担当者の有無
「中小企業の法務対応に関する調査」でスモールビジネスにおける法務担当者の有無についてたずねた所、次のような結果でした。
| 担当者の有無 | 割合 |
| 設置していない | 67.2% |
| 兼任の担当者がいる | 25.6% |
| 専任の担当者がいる | 8.3% |
また「兼任の担当者がいる」「専任の担当者がいる」と回答した企業にその人数をたずねた結果は次の通りです。
| 回答内容 | 人数 | 割合 |
| 兼任の担当者がいる | 6人以上 | 1.0% |
| 5人 | 0.5% | |
| 4人 | 2.5% | |
| 3人 | 3.5% | |
| 2人 | 20.9% | |
| 1人 | 71.6% | |
| 専任の担当者がいる | 6人以上 | 12.7% |
| 5人 | 1.4% | |
| 4人 | 1.4% | |
| 3人 | 5.6% | |
| 2人 | 21.1% | |
| 1人 | 57.7% |
専任でも兼任でも担当者が1人しかいないことが多く、人材不足を法務の課題として挙げる企業が多いのを裏付ける結果となっています。
法的課題の相談先
「中小企業の法務対応に関する調査」でさまざまな法的課題や疑問が生じた時誰に相談するかをたずねた所、次のような結果でした。
| 相談先 | 割合 |
| 税理士 | 54.7% |
| 顧問弁護士 | 44.8% |
| 顧問弁護士ではない外部の弁護士 | 29.4% |
| 社会保険労務士 | 29.9% |
| 司法書士 | 15.1% |
相談先が顧問弁護士一択ではなく、分散しているのが特徴的と言えるでしょう。
株式会社KAKERUではスモールビジネスの法務相談を適切な専門家に行えるようサポートします
株式会社ではスモールビジネスにおける法務相談を、適切な専門家に対して行えるようサポートしています。
前の項目のアンケート結果でもわかる通り、スモールビジネスでは法務の専門担当を設置するのが難しいため、法的課題が生じた時どうしても外部の専門家に相談する機会が増えるでしょう。
課題の内容によってはどこに相談すればよいのかを判断しにくい場合がありますが、このような時でも株式会社KAKERUではバックオフィス業務全体をサポートした経験から、適切な提携先へとご紹介が可能です。
法的課題が生じた際の窓口として、株式会社KAKERUへお気軽にご相談ください。
”〇〇”がさらに楽しくなる仕掛けを創る – 株式会社KAKERU (kaxeru-office.com)
まとめ
法務とは法律に携わる事務、職務、業務のことで、企業において行われる法務は「企業法務」と呼ばれ法務部がその業務を担当します。
この記事も参考にして、スモールビジネスにおける法務がスムーズに行えるよう準備を整えてみてください。